
「自分で視聴した動画も再生回数に入るんかな?」
YouTubeに作成した動画をアップしていると、ふとこんな疑問が浮かんだことはありませんか。
せっかく頑張って作った動画、「ちょっと確認」と何度も自分で見たものの、それが良いのか悪いのか気になりますよね。
このような疑問に、この記事ではとことんお答えします!
YouTubeでの「自分の再生」が再生回数に含まれる仕組みとは?
結論から言うと、YouTubeでは条件次第で自分の視聴も再生回数に含まれるのです。
ですが、「再生すれば即カウント!」という単純なものではありません。YouTubeは独自のアルゴリズムとシステムで、再生の“質”を厳密にチェックしています。
視聴回数の基本ルールとカウント条件を理解する
再生回数の計上には、いくつかの重要な基準が存在します。
YouTubeの公式ガイドラインでは明確な数値を示していませんが、業界の分析や公式の発表から見えてくる共通点があります。
まず、視聴がカウントされるためには「意図的な再生」であることが前提です。ユーザーが自ら操作して動画を再生し、その動画を“きちんと見た”と判断される必要があります。
というわけで、動画を開いた直後にすぐ閉じたような再生、つまり視聴時間が短すぎる場合は、再生回数として無効になることがあります。
短時間で停止したり、スキップされたりした再生はカウントされにくく、最低30秒程度の視聴が一つの目安とされています。
YouTubeアナリティクスでの再生回数の扱い方
YouTubeで動画をアップしたら、やっぱり気になるのが「どれだけ見られているか」ですよね。

YouTube始めたての頃は、気になってずっとアナリティクス見てました。
そんなときに頼りになるのが「YouTubeアナリティクス」。
しかし、初期設定のままだと自分の視聴も再生回数や視聴者データに含まれてしまう可能性があります。自分で動画を頻繁にチェックする人は、アナリティクスの数字が実際の視聴傾向を反映していないことも…。
この問題を避けるには、自分の視聴をアナリティクスから除外する設定が必要です。例えば、GoogleタグマネージャーやIP除外設定を使えば、同一IPからのアクセスを無視することが可能です。
また、YouTube Studio内で「リアルタイム視聴」や「トラフィックソース」などの指標をチェックすることで、自分のアクセスがどこまで反映されているかを推測することもできます。
「YouTubeアナリティクスを正しく読む力」は、チャンネル運営の根幹と言っても過言ではありません。
ここで注意すべきなのは、再生回数だけを鵜呑みにせず、「平均視聴時間」や「視聴者維持率」などの他の指標と合わせて評価すること。
これにより、自分の再生の影響を最小限にしつつ、よりリアルな分析が可能になります。
自分の視聴が反映されない再生回数のNGパターンとは?
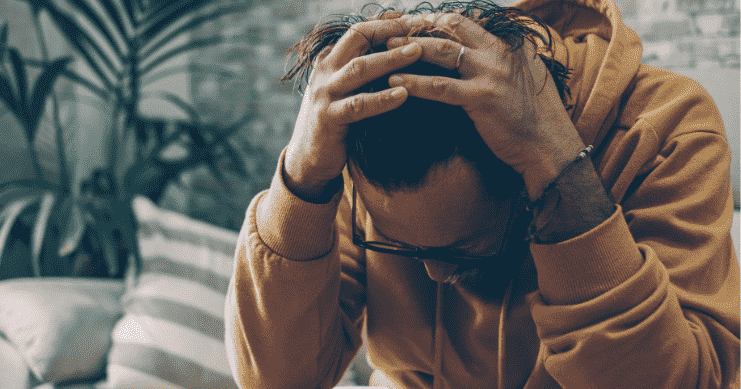
どんなに再生ボタンを押しても、カウントされない…。それには、明確な理由があります。
YouTubeには「これは再生とは認めません!」というNGパターンがいくつもあるんです!
まず代表的なのが、短時間で同じ動画を何度も再生する行為。これ、たとえ手動であっても「視聴を水増ししようとしてるのでは?」とアルゴリズムに判断され、重複扱いでカウント対象外になることがよくあります。
そして次に重要なのが、動画を開いてすぐ閉じる=短時間視聴。YouTubeは視聴時間もカウントの条件にしており、一般的には「30秒以上」が1つの基準とされています。つまり、「ちょっと開いてすぐ戻っただけ」では、再生回数にはなりません。
さらに、自動再生やリロード操作での再生もNGです。再読み込みを連打するような動きはBotのような挙動と見なされやすく、完全にカットされるケースが多いんですね。
YouTubeではIPアドレスやデバイスIDを活用して再生を識別しています。同じ端末、同じネットワークからの連続視聴は、意図的な水増しと判断されやすいため、実質的に再生数として無効になるケースが多いのです。
こうした不正とみなされる行為は、再生回数が増えないだけでなく、アカウントの信頼性を落とす原因にもなります。
ちなみに、自作自演の視聴を実験してみた結果がこちらです。↓↓
YouTubeのガイドラインには明記されていませんが、信頼性の低いアカウントと判断された場合、動画の露出が下がることもあるんです。
「やってないのに…」と心当たりがないユーザーでも、無意識のうちにこのNGパターンを踏んでしまっているケースが多々あります。
YouTubeの規約に抵触する視聴方法を避ける
再生回数を増やしたい気持ちはとても良く分かります。でも、その努力が思わぬ形でYouTubeの利用規約に触れてしまうことも…。
YouTubeでは「不正なトラフィック」や「操作された指標の操作」を厳しく取り締まっており、その対象に過剰な自作自演再生が含まれるんです!
まず避けるべきなのが、短時間に同一IPアドレスから何度も再生する行為。これは、手動であってもアルゴリズムからすれば「人工的な操作」と見なされる可能性が大。
そして要注意なのが、複数アカウントを使って自分の動画を再生すること。一見工夫のようにも思えますが、これは明確に「視聴指標の操作」とされ、YouTubeポリシー違反となるリスクがあります。最悪の場合、動画の削除やチャンネルの制限措置がとられることも…。
さらに、「再生数を増やすためのサービス」を購入するのも完全にアウト!これらの行為はGoogleの不正検出システムによって追跡され、瞬時に無効化されるだけでなく、信頼性の低下によって関連動画や検索表示にも悪影響を及ぼします。
結局のところ、視聴者にとって価値のある動画を作り、自然な再生を得ることこそが、長期的にチャンネルを育てる王道なのです。
「規約を知らなかった」では済まされないこともあるので、慎重な行動を心がけましょう!
“自分のアクセスを除外する”とは?

YouTubeアナリティクスを最大限に活用するには、自分の視聴を除外することが重要です。
特に、動画の内容確認やチェック目的で何度も再生する制作者自身は、アナリティクスに自分の行動が反映されてしまうと、「本当に視聴者が見てくれたのかどうか」が曖昧になります。
これでは、視聴者のリアルな反応を掴むことが難しくなってしまいますよね。
そこで活用すべきなのが、GoogleタグマネージャーやIPフィルタリングを用いた除外設定です。Googleアナリティクス(GA4)と連携している場合、自分や関係者のIPアドレスを指定してフィルタをかけることで、自分のアクセスを正確に除外できます。
また、Chromeの拡張機能を使って、自分のアクセスを除外する方法もあります。例えばGoogle Analytics オプトアウト アドオンなどを導入すれば、自分が行った視聴や操作が記録されなくなります。
信頼できるデータをもとに改善を図るためにも、自分の視聴は分析から切り離すべきなのです。
まとめ:自分の視聴がカウントされる条件を正しく理解しよう
YouTubeでは、自分の視聴が再生回数に含まれることもありますが、常にカウントされるわけではありません。
30秒以上の自然な視聴であれば反映される可能性が高い一方、短時間視聴やリロード、同一IPアドレスからの繰り返し再生は無効になることがあります。
また、アナリティクスで正確なデータを得るには、自分のアクセスを除外する設定や分析の工夫が必要です。自作自演による再生操作は規約違反と見なされ、チャンネルに悪影響を与えるリスクもあります。
健全なチャンネル運営のためには、アルゴリズムの特性を理解し、ユーザーの関心を引く動画づくりに集中することが最も効果的です。
数字にとらわれすぎず、視聴者との信頼を築きながら、長期的なチャンネルの成長を目指しましょう!

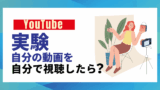
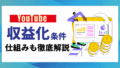
コメント