さて皆さん、こんにちは。
2025年7月15日、YouTubeが発表したポリシー改正は、多くのクリエイターに不安をもたらしていることと思います。「自分の動画は大丈夫なのだろうか?」とドキドキしている方もいるのではないでしょうか。

かくいう私もその一人です、、
“AI動画終了!”のような見出しも多く見受けられますが、まず初めにお伝えしておきたいのは、今回のポリシー改正は、新しいポリシーの導入ではなく、小規模な更新ということです。
では、どういう点に変更があったのかについて、詳しく見ていきましょう!
YouTubeポリシーの変更点をわかりやすく解説
今回のポリシー変更では、「量産型のコンテンツ」がYouTubeの収益化対象から外れるケースが明示されました。
量産型とは、構成や表現が似通った動画を大量に投稿することで、短期間で再生回数を稼ごうとするコンテンツ形式のこと。
では、どんな動画が量産型と見なされるのでしょうか?ポイントは大きく3つです。
まず1つ目は、「内容に独自性がないこと」。例えば、テンプレート化されたBGMや読み上げ音声に、文字だけのスライドショー動画。こうした動画は、見た目や構造がほぼ同じであるため、視聴者に新たな価値を提供していないと見なされやすいのです。
2つ目は、「過度な投稿頻度」。毎日似たようなフォーマットで動画を投稿すること自体がアウトではありませんが、内容に差異がなければ「AIや自動生成で作られている」と疑われる可能性があります。
3つ目は、「視聴者エンゲージメントの低さ」。コメント数や視聴維持率が著しく低い動画は、「視聴者に価値を感じてもらえていない=中身が薄い」と判断される可能性が高いです。
今回の改正で最も重要なのは、「形式」ではなく「中身」が重視されるという点です。
つまり、AIを使っていても、オリジナリティがあり、しっかりと編集やナレーションが施されていればOK。
逆に、人間が作っていても、構成が画一的ならNGの可能性があるということですね。
“再利用コンテンツ”との違いとは?両ポリシーの比較と線引きポイント
「量産型コンテンツ」と「再利用コンテンツ」。似たような響きですが、YouTubeにおけるこの2つのポリシーには明確な違いがあります。
まず、「再利用コンテンツ」とは、他人の動画素材を再編集して投稿する場合に適用されるポリシーです。
たとえば、テレビ番組のクリップや他のYouTuberの映像を再利用して、自分のチャンネルで公開するケースがこれに該当します。解説動画や、リアクション動画などもそうですね。
ここで求められるのは、「付加価値」があるかどうか。つまり、単に映像をつなぎ合わせるだけではなく、自分の解説・分析・演出がしっかり含まれていることが条件です。
一方、「量産型コンテンツ」は、自分で作成した動画でも、「中身の薄い、似たような構成の動画を延々と繰り返し投稿している場合」に適用されます。
つまり、自作かどうかは関係なく、「新しい視聴体験があるか」が問われているのです。
- 再利用コンテンツは“他人の素材”をどう料理(編集)するかが問われる
- 量産型コンテンツは“自作の質”と“バリエーション”が問われる
たとえば、クリップに自分の意見を付け加えた「リアクション動画」や、複数の情報を解説した「まとめ動画」などは、しっかりと編集と視点が加えられていれば、「再利用コンテンツ」として収益化の可能性は十分あります。
一方で、「ナレーションが同じで、画像だけ差し替えた10本の動画」や「内容に変化がないリーディング動画」などは、たとえ素材がすべて自作でも「量産型」とみなされ、収益化審査で却下されるかもしれませんね。
「自分の動画、どっちに当てはまるの?!」という方も多いと思います。次章では、それを見極めるための具体的な判断軸と、対策の立て方をご紹介します。
AIやAI音声の扱いはどうなる?
今回のポリシー変更では、下記で公式も言及しているように、「AIの使用そのもの」を禁止しているわけではなく、「AIで量産された、価値の薄いコンテンツ」が問題視されているのです。
YouTube は、AI ツールを使用してストーリーテリングを強化しているクリエイターを歓迎しています。コンテンツ制作に AI を活用しているチャンネルも、引き続き収益化の対象となります。
引用元 | YouTubeヘルプ公式 より
例えば、AI音声をナレーションに用いた動画であっても、しっかりとした台本があり、視聴者の理解を深めるような解説や補足が含まれていれば、収益化の対象になり得ます。
逆に、「画像をただスライド形式で並べて、BGMとAI音声を付けただけ」のような動画は要注意かもしれません。こうしたコンテンツは、視聴者にとっての体験価値が乏しく、量産型と見なされやすいのです。

YouTubeとしても、工夫しているクリエイターに報酬を払いたいということか!
YouTubeは近年、「ユーザーの信頼を得るクリエイターへの還元」を重視しており、動画の作り手がどれだけ真摯に視聴者と向き合っているかを見ています。
AIはあくまでも「補助的ツール」として位置付け、自分自身の解釈や工夫、演出を加えることが求められるのです。
今後の収益化審査に向けて、より一層「自分の視点」や「視聴者との対話」を意識したコンテンツ作りに取り組むことが求められるでしょう。
【まとめ】これからのYouTube運用は?
今回のポリシー改正によって、YouTubeは「誰でも同じような動画を並べて稼げる時代」の終わりをより明確にしました。
収益化において重要視されるのは、「本物の価値あるコンテンツ」を提供しているかどうか。その本質がより厳格に、かつ可視化された形で示されたのです。
とはいえ、「AIがダメ」「自動音声がNG」といった表層的な解釈ではなく、あくまで問題は“中身”と“視聴者体験”の質。
つまり、
- 自分の言葉で伝える工夫があるか?
- 見る価値があると思わせる構成になっているか?
- 視聴者とのつながりを感じられる動画になっているか?
この3点を満たしていれば、AIを使っていても、テンプレ要素があっても、収益化の可能性は十分にあります。
今後は「大量に作る」のではなく、「1本ずつ丁寧に届ける」ことが重視される時代になりそうですね。
視聴者の「見てよかった!」という感覚こそが、収益化の本当のカギなのです。次の動画づくりに向けて、ぜひ今一度、自分のチャンネルを見直してみてください。

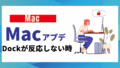
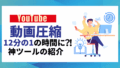
コメント